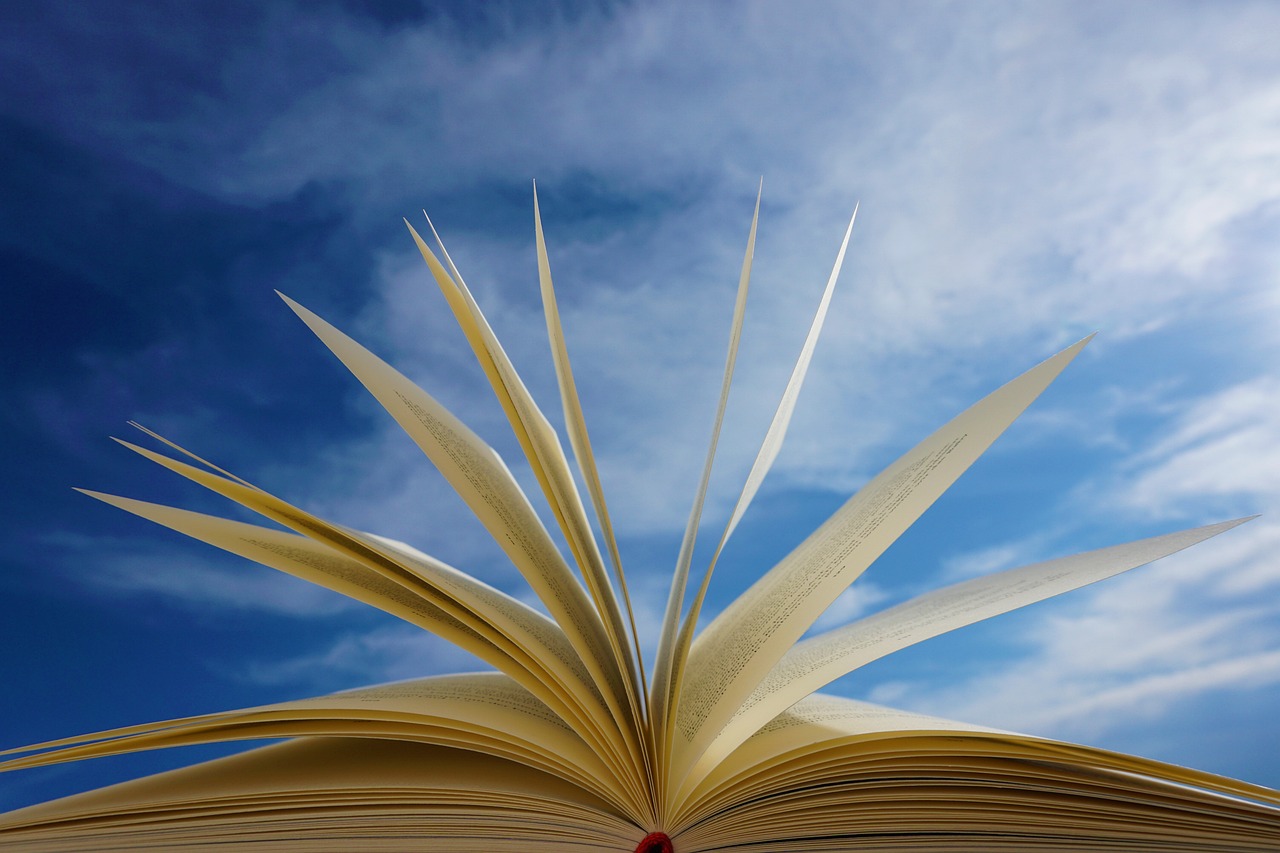皆さんは「成績はいいけど、勉強が身についている気がしない…」と思ったことはありませんか?
私もまさにそんな学生のひとりでした。今回は、学部時代の“勉強の失敗”を振り返りながら、「今ならどう勉強するか?」をお伝えします。
この記事は、以下の方のために書いています。
- GPAは高いのに学力に自信がない…
- 大学院でついていけないと感じている…
大学生時代の勉強の失敗談
GPAをとることしか考えてなかった
皆さんは、小中高時代、何のために勉強していましたか?
私は「良い成績をとって、周囲から尊敬されるための手段」だと考えていました。
多くの人がそうであるように、小中高では「ペーパーテストで良い点をとる=優秀」という価値観を自然と刷り込まれていきます。私も例に漏れず、その価値観にどっぷり浸かっていました。
そうやって大学に入る頃には、私の中には「成績こそが優秀さの証だ」という価値観が、完全に染み付いてしまっていました。
その結果、大学では「どうすればGPAを上げられるか」ばかりを考えるように。
面白そうでも難しそうな授業は避け、教科書をただ読むだけの勉強、演習もテストに出そうな簡単な問題しかやらない。そんな日々を送っていました。
大学のテストは、正直言えば解法暗記と過去問さえあれば乗り切れてしまうことも多いです。だからこそ、「GPAをとる勉強」をしていると、本質的な学問の理解がどんどん疎かになっていくのです。
今振り返ると、GPAにとらわれていたことが、私の学びにとって最も有害だったと思います。
GPAが役立つ場面はほとんどないですし、だったらもっと色々な授業を取っておけば良かったと後悔しています。
勉強について話せる友達がいなかった
私が所属していた物理学科には、50人ほどの学生がいました。
成績という観点では、私は上位に入っていたと自負しています。
そのせいか、友達から勉強について質問されることはあっても、自分から「教えてほしい」と言うことはほとんどありませんでした。
理由は、謎のプライドと、ちょっとした人見知りです。
明らかに自分より優秀そうな人がいても、「話しかけるのが怖い」「優秀な人の前で自分が恥をかくのが怖い」「聞いたら負けだ」という変な意識があったんです。
つまり、私は心のどこかで「自分はできる方だから、わざわざ誰かに聞く必要はない」と思っていたんですね。(今思うと、なんて傲慢だったんでしょう…)
その結果、教科書でわからない部分があっても、誰にも聞けない。
仕方なく、お茶を濁して曖昧に理解するか、最初から諦めるかの二択を繰り返していました。
心では、物理を一緒に議論できる友達が欲しいと思っていたのに、プライドが邪魔して結局できなかったことにとても後悔しています。
このプライドも、成績を重視する価値観から生まれたものです。
大学院生になって勉強を振り返る
研究を続ける中で実感したのは、「知識は使えるようになって初めて意味を持つ」ということです。
ただ覚えるだけではなく、生活や実社会の中で応用できたり、自分の直感や判断力のベースになって初めて、それは本当の知識になります。そうした知識こそが面白く、価値のあるものだと断言できます。
私にとって、勉強の本質とは、「知識を蓄え、応用し、それを活かして自分にも他人にも貢献すること」だと考えています。
この考えをもとに、私が勉強において大切だと感じていることを、以下にまとめてみました。
自分の体験に紐づいた勉強をする
この方法は、勉強を「つまらない作業」から「ワクワクする体験」に変えてくれます。
私自身、このやり方を取り入れてから、学びがグッと楽しくなりました。
たとえば、物理の「電磁誘導」という現象。
これは、磁場が変化すると電場が生じ、金属に電流が流れるという仕組みです。
でも、教科書でこの説明だけ読んでも、正直あまり面白くありませんよね。
ただ、実はこの原理、トラックやバスのブレーキ、IHコンロなど、私たちの身近な技術に活かされているんです。そう聞くと、少し面白いと思いませんか?
自分の生活とつながっていることを知ると、「ただの現象」が一気に「役に立つ知識」に変わります。
さらに、こうした現象を「実際に目で見ること」も効果的です。
自分で実験してみるのもいいですが、手軽にYouTubeで実験動画を見るだけでも、理解が深まります。
理科の実験って、小中学校のころは意外と楽しかったですよね。
あれは「自分で体験する」からこそ、楽しかったんだと思います。
つまり、「教科書で覚えなきゃ」と思うから勉強がつまらなくなる。
でも、自分の体験や興味とつなげることで、勉強は一気に面白くなるんです。
私はこれを研究から学びました。
最初はよくわからないまま実験装置を動かしてデータを取っていたのですが、その段階で改めて教科書を読み直してみると、無味乾燥だった文字の羅列の中にたくさんの研究に役立つ情報が含まれていて、教科書を読むのが趣味になるくらい勉強が面白く感じるようになったのです!(マジで!!)。
勉強の必要性を作る
もう一つ大切なのが、「勉強せざるを得ない環境」を自分から作ることです。
つまり、「やらなきゃ」と無意識に感じる状況に飛び込むこと。
たとえば、将来アメリカに住みたいと思っていたら、英語は必須です。
このとき、「いつか必要になるから英語の勉強をしよう」と思うよりも、ネイティブと話す環境に飛び込んで、「英語を使わないと困る状況」を自分で作る方が圧倒的に学習が効率的になります。
学校にいるネイティブの先生と積極的に話したり、思い切って留学したりするのも良い方法です。
ポイントは2つ。「自分から飛び込む勇気」と「逃げ出さずに続ける勇気」です。
この「必要性」は、学習における最重要ポイントだと感じています。
なぜなら、研究室に入って「成果を出さなければいけない」状況になってから、明らかに勉強の定着率が上がったからです。
物理にしても英語にしても、学部時代よりはるかに効率的に身につくようになりました。
「やらなきゃいけない」環境が、勉強の質を変えてくれたのだと思います。
まとめ
大学院に入って気づいた、勉強を効率的に続けるために重要なのは
- 勉強を楽しくするため、自分の体験と紐づける
- 勉強をしないと生きていけないくらいの環境に自ら飛び込み、逃げ出さないでやり続けること