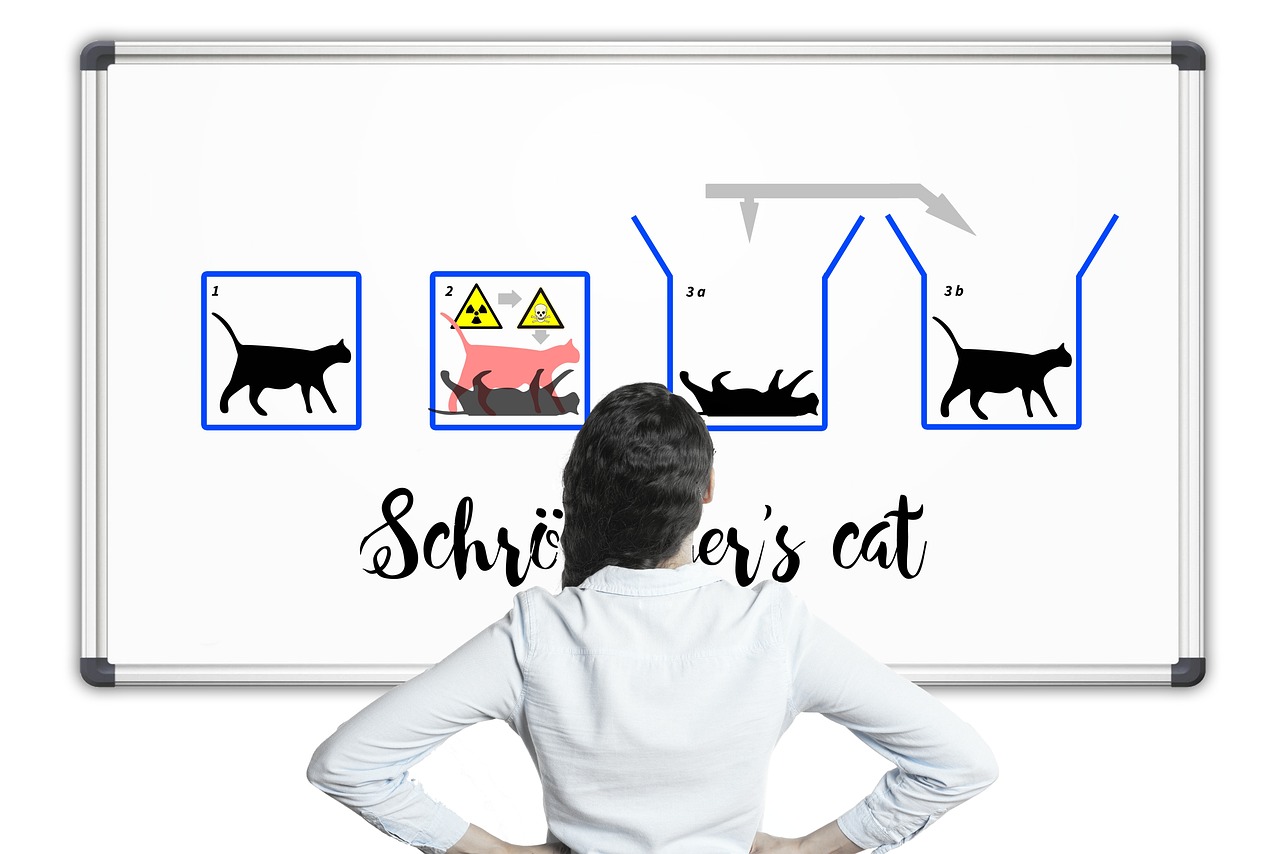理系大学生や、文学を読むのが好きな方のために、こちらのページで無料で多数の本が読めるリンクをまとめています。非常に有益ですので是非お読みください。
3次元調和振動子の動径方向のシュレーディンガー方程式
3次元調和振動子の問題は、極座標を用います。以下の知識を前提として話を進めるので、分からない方は一旦認めてもらって、後で教科書などで確認をお願いします。
まず3次元調和振動子のポテンシャルは
$$ \frac{1}{2} mw^2r^2$$
で表されます。これにより、波動関数を動径方向と角度方向に変数分離した後の、動径方向のシュレーディンガー方程式は以下の形をとります。
$$ \frac{r^2}{R(r)} \frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} (rR(r)) + \frac{2m}{\hbar^2} (E- \frac{1}{2} mw^2r^2) r^2 = \lambda(=const)$$
ただし、$$ \lambda = \ell(\ell +1)$$ です(後で使います)。
rについての微分方程式にする
r方向の微分について
$$ \frac{\partial}{\partial r}(rR(r))=R+r \frac{dR}{dr}$$
となることから、二階微分は
$$ \frac{\partial^2}{\partial r^2} (rR(r))=\frac{\partial}{\partial r}(R+r \frac{dR}{dr})=2\frac{dR}{dr}+r\frac{d^2 R}{dr^2}$$
となります。したがってこれらを先ほどの微分方程式に代入すると
$$ \frac{r}{R} (2\frac{dR}{dr}+r\frac{d^2 R}{dr^2})+ \frac{2m}{\hbar^2} (E- \frac{1}{2} mw^2r^2) r^2 = \lambda$$
となり、これを変形して
$$ \frac{d^2 R}{dr^2}+\frac{2}{r} \frac{dR}{dr}+\frac{2m}{\hbar^2}(E-\frac{1}{2}mw^2r^2-\frac{\lambda \hbar^2}{2m r^2})R=0$$
という目的の微分方程式が得られます。
ρについての微分方程式にする
このrについての微分方程式をρに変数変換して、この新しい変数についての微分方程式を導きます。
具体的にはρの変数変換の式は
$$ \rho=\sqrt{\frac{m \omega}{\hbar}}r$$
で与えられます。そして、この変数変換の式から
$$ \frac{d\rho}{dr}=\sqrt{\frac{m \omega}{\hbar}}$$
が導かれるので、微分記号の変換は以下の通りになります。
$$ \frac{d}{dr}=\frac{d \rho}{dr} \frac{d}{d \rho}=\sqrt{\frac{m \omega}{\hbar}} \frac{d}{d \rho}$$
$$ \frac{d^2}{dr^2}=\sqrt{\frac{m \omega}{\hbar}} \frac{d}{d \rho} \sqrt{\frac{m \omega}{\hbar}} \frac{d}{d \rho}= \frac{m \omega}{\hbar} \frac{d^2}{dρ^2}$$
これらの三つの式をrについての微分方程式に代入します。個別にひとつづつやっていくと
$$ \frac{d^2 R}{dr^2}=\frac{m\omega}{\hbar} \frac{d^2 R}{d\rho^2}$$
$$ \frac{2}{r} \frac{dR}{dr}=\frac{2m\omega}{\hbar} \frac{1}{\rho} \frac{dR}{d\rho}$$
$$ \frac{2m}{\hbar^2}(E-\frac{1}{2}mw^2r^2-\frac{\lambda \hbar^2}{2m r^2})R=\frac{2m}{\hbar^2}(E-\frac{1}{2}\hbar \omega \rho^2- \frac{1}{2} \lambda \hbar \omega \frac{1}{\rho^2})R$$
となるので、これらを足し合わせて
$$ \frac{m\omega}{\hbar} \frac{d^2 R}{d\rho^2}+\frac{2m\omega}{\hbar} \frac{1}{\rho} \frac{dR}{d\rho} +\frac{2m}{\hbar^2}(E-\frac{1}{2}\hbar \omega \rho^2 -\frac{1}{2} \lambda \hbar \omega \frac{1}{\rho^2})R=0$$
この式を整理すると、求めたかったρについての微分方程式
$$ \frac{d^2 R}{d\rho^2}+ \frac{2}{\rho} \frac{dR}{d\rho} +\frac{2}{\hbar \omega}(E-\frac{1}{2}\hbar \omega \rho^2 – \frac{1}{2} \lambda \hbar \omega \frac{1}{\rho^2})R=0$$
が導かれました。
ξについての微分方程式にする
次は、ρの微分方程式をξについての微分方程式にします。ξは「クシー」や「クサイ」「グザイ」などと読みます。
rの微分方程式をρに変えたのと同様の手順をとります。
まず、ξの変数変換の式は
$$\xi=\rho^2$$
です。したがって、
$$ \frac{d\xi}{d\rho}=2\rho=2\sqrt{\xi}$$
これから微分記号を求めます。先ほどのρとは少し違うので注意してください(やり方は同じ)。
$$ \frac{d}{d\rho}=\frac{d\xi}{d\rho} \frac{d}{d\xi}=2\rho \frac{d}{d\xi}=2\sqrt{\xi} \frac{d}{d\xi}$$
$$ \frac{d^2}{d\rho^2}=2\sqrt{\xi} \frac{d}{d\xi} (2\sqrt{\xi} \frac{d}{d\xi})=4\sqrt{\xi} \frac{d}{d\xi}(\sqrt{\xi} \frac{d}{d\xi})=2\frac{d}{d\xi}+4\rho^2 \frac{d^2}{d\xi^2}$$
これらを用いて微分方程式を書き換えます。先ほどと同様個別に見ていきます。
$$ \frac{d^2 R}{d\rho^2}=4\xi \frac{d^2 R}{d\xi^2}+2\frac{dR}{d\xi}$$
$$ \frac{2}{\rho} \frac{dR}{d\rho}=4\frac{dR}{d\rho}$$
$$ \frac{2}{\hbar \omega}(E-\frac{1}{2}\hbar \omega \rho^2 – \frac{1}{2} \lambda \hbar \omega \frac{1}{\rho^2})R=\frac{2}{\hbar \omega}(E-\frac{1}{2}\hbar \omega \xi – \frac{1}{2} \lambda \hbar \omega \frac{1}{\xi})R$$
これらを足し合わせると
$$ 4\xi \frac{d^2 R}{d\xi^2}+2\frac{dR}{d\xi} +4\frac{dR}{d\xi} +\frac{2}{\hbar \omega}(E-\frac{1}{2} \hbar \omega \xi -\frac{1}{2} \lambda \hbar \omega \frac{1}{\xi})R=0$$
が得られます。これを整理すると目的のξについての微分方程式
$$ \frac{d^2 R}{d\xi^2}+\frac{3}{2} \frac{1}{\xi} \frac{dR}{d\xi} + \frac{1}{2\hbar \omega} \frac{1}{\xi}(E-\frac{1}{2} \hbar \omega \xi -\frac{1}{2} \lambda \hbar \omega \frac{1}{\xi})R=0$$
が導かれます。
Rの式を仮定して、ξについての微分方程式からf(ξ)の微分方程式にする
ここで、R(ξ)の式を
$$ R(\xi)=e^{-\xi/2} \xi^{\ell/2} f(\xi)$$
と仮定します。これをξについての式に代入して、f(ξ)についての微分方程式にするのがこの節の目的です。これによって、合流型超幾何微分方程式に持ち込むことができます。
手計算でやると、かなり大変です
まずはRをξで微分しましょう。
$$ \frac{dR}{d\xi}=\frac{d}{d\xi}(e^{-\xi/2} \xi^{\ell/2} f(\xi))=e^{-\xi/2} \xi^{\ell/2 -2}(-\frac{1}{2} \xi^2 f+\frac{1}{2} \ell \xi f+\xi^2 \frac{df}{d\xi})$$
となります。これから二階微分を求めます。上の一階微分の結果を微分すれば良いだけなので、結果だけ載せます。
$$ \frac{d^2 R}{d\xi^2}=e^{-\xi/2} \xi^{\ell/2 -2}[\frac{1}{4} \xi^2 f -\frac{\ell}{2} \xi f-\xi^2 \frac{df}{d\xi} + \frac{\ell}{2} (\frac{\ell}{2}-1)f+\ell \xi f+\xi^2 \frac{d^2 f}{d\xi^2}]$$
これらより
$$ \frac{3}{2} \frac{1}{\xi} \frac{dR}{d\xi}=e^{-\xi/2} \xi^{\ell/2 -2}(-\frac{3}{4} \xi f+\frac{3}{4} \ell f+\frac{3}{2} \xi \frac{df}{d\xi})$$
$$\frac{1}{2\hbar \omega} \frac{1}{\xi}(E-\frac{1}{2} \hbar \omega \xi -\frac{1}{2} \lambda \hbar \omega \frac{1}{\xi})R=e^{-\xi/2} \xi^{\ell/2 -2}(\frac{E}{2\hbar \omega} \xi f-\frac{1}{4} \xi^2 f -\frac{\lambda}{4}f)$$
であるから、これらを用いて(足し合わせて)ξの微分方程式を書き換えると
$$ e^{-\xi/2} \xi^{\ell/2 -2}[{-\frac{1}{4}(2\ell +3)+\frac{E}{2\hbar \omega}}\xi f+\frac{1}{4} {\ell (\ell +1)-\lambda}f \\+ {(\ell +\frac{3}{2})-\xi}\xi \frac{df}{d\xi}-\xi^2 \frac{d^2 f}{d\xi^2}]=0$$
したがってこの式に$$ \lambda = \ell(\ell +1)$$を代入し、式を整理すると求めたいf(ξ)についての微分方程式
$$ \xi \frac{d^2 f}{d\xi^2}+[(\ell +\frac{3}{2})-\xi]\frac{df}{d\xi}-[\frac{1}{4} (2\ell +3)-\frac{E}{2\hbar \omega}]f=0$$
を導くことができます。
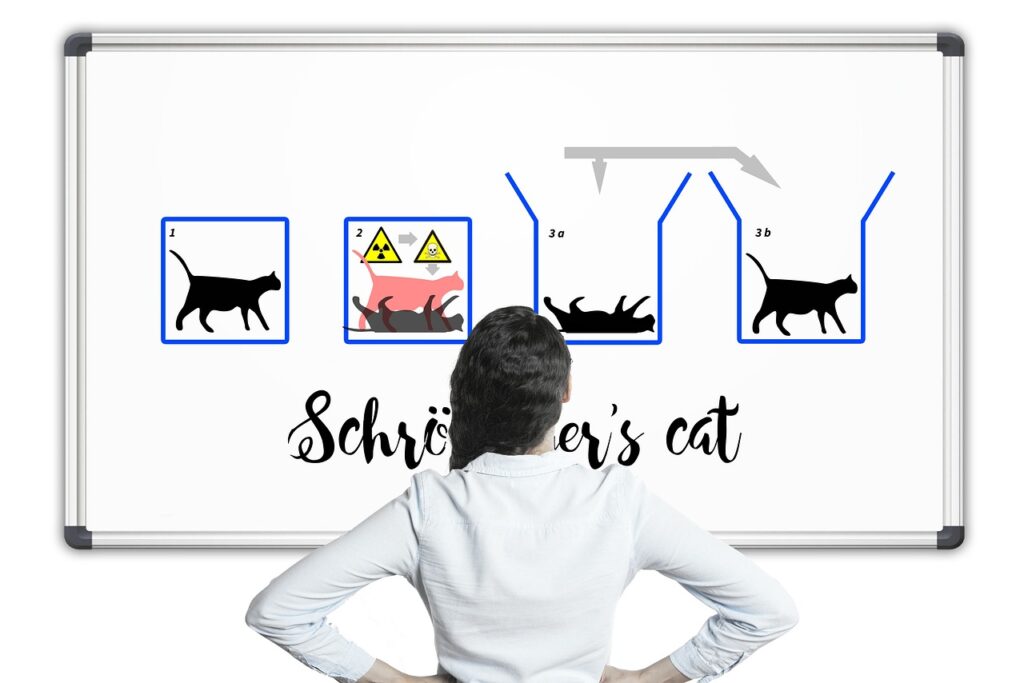
合流型超幾何微分方程式
f(ξ)の微分方程式と合流型超幾何微分方程式の比較
合流型超幾何微分方程式:
$$ z\frac{d^2}{dz^2}u(z)+(\gamma -z)\frac{d}{dz}u(z)-\alpha u(z)=0$$
という微分方程式があります。導いたf(ξ)についての微分方程式と見比べてみましょう。
$$ \xi \frac{d^2}{d\xi^2}f(\xi)+[(\ell +\frac{3}{2})-\xi]\frac{d}{d\xi}f(\xi)-[\frac{1}{4} (2\ell +3)-\frac{E}{2\hbar \omega}]f(\xi)=0$$
$$ z\frac{d^2}{dz^2}u(z)+(\gamma -z)\frac{d}{dz}u(z)-\alpha u(z)=0$$
比較すると
$$ z=\xi$$
$$\gamma=\ell +\frac{3}{2}$$
$$\alpha=\frac{1}{4} (2\ell +3)-\frac{E}{2\hbar \omega}$$
と置けば全く同じ形であることが分かります。
したがって、このf(ξ)についての微分方程式に合流型超幾何微分方程式の性質を適用することが可能です。
合流型超幾何微分方程式の性質
$$ z\frac{d^2}{dz^2}u(z)+(\gamma -z)\frac{d}{dz}u(z)-\alpha u(z)=0$$
この方程式の解で、原点で正則な解を$$F(\alpha;\gamma;z)$$と書いて、これを合流型超幾何関数と呼びます。
zを無限大に発散させる極限(z→∞)で合流型超幾何関数が多項式になるための条件は
$$\alpha=-n \qquad (n=0,1,2,3,\cdots)$$
となります。
エネルギー固有値を求める
この性質を使えば、簡単にエネルギー固有値を求めることができます。なぜならもうすでに私たちはαについての二つの式を得ているからです。
$$\alpha=\frac{1}{4} (2\ell +3)-\frac{E}{2\hbar \omega}=-n$$
この式をEについて解けば
$$E=\hbar \omega (2n+\ell+\frac{3}{2})$$
となります。この式から縮退するのは
$$2n+\ell=const$$のときのペアだと言えます。
波動関数を求める
最初に波動関数を動径方向と角度方向に変数分離しました:
$$ \psi(r,\theta,\phi)=R(r)Y_{\ell m}(\theta,\phi)$$
また、動径方向の成分について以下の仮定をしました:
$$ R(\xi)=e^{-\xi/2} \xi^{\ell/2} f(\xi)$$
このとき、f(ξ)の微分方程式は合流型超幾何微分方程式の解となっていたことがこれまでの議論で分かりました。よって、f(ξ)は合流型超幾何関数です。
以上より、求める波動関数はξを変数とすると
$$ \psi(\xi,\theta,\phi)=e^{-\xi/2} \xi^{\ell/2} F(\alpha;\gamma;\xi) Y_{\ell m}(\theta,\phi)$$
となります。
変数変換の式$$\xi=\rho^2$$を思い出せば、ρを変数とすると
$$ \psi(\rho,\theta,\phi)=e^{-\rho^2 /2} \rho^{\ell} F(\alpha;\gamma;\rho) Y_{\ell m}(\theta,\phi)$$
となります。
※波動関数は規格化をしていません。ご注意ください

基底状態、第一励起状態、第二励起状態
基準としては$$2n+\ell=const$$を満たすかどうかです
基底状態
これは最低のエネルギー順位なので、$$(n,\ell)=(0,0)$$のときです。
エネルギーは$$E=\hbar \omega (2 \times 0 +0 +\frac{3}{2})=\frac{3}{2} \hbar \omega$$となります。
このとき波動関数は
$$R=e^{-\rho^2 /2} \qquad , \qquad \psi=e^{-\rho^2} \qquad (m=0)$$
となります。
このときℓ=0なのでm=0のみとなり、縮退度は1です。
第一励起状態
$$(n,\ell)=(0,1)$$のときです。
エネルギーは$$E=\hbar \omega (2 \times 0 +1 +\frac{3}{2})=\frac{5}{2} \hbar \omega$$となります。
波動関数は
$$R=e^{-\rho^2 /2} \rho \qquad , \qquad \psi=e^{-\rho^2} \rho Y_{1m}(\theta,\phi) \qquad (m=0,\pm 1)$$となります。
ℓ=1なのでmの絶対値は0,1の両方をとれることから、mの値は三つあります。
したがって、縮退度は3です。
第二励起状態
$$(n,\ell)=(1,0),(0,2)$$のときです。このときエネルギーの表記(2n+ℓの部分)を見れば確かに同じエネルギーを与えることが分かります。
(n,ℓ)=(1,0)のとき
エネルギーは$$E=\hbar \omega (2 \times 1 +0 +\frac{3}{2})=\frac{7}{2} \hbar \omega$$となります。
波動関数は
$$R=e^{-\rho^2 /2} (\frac{3}{2}-\rho^2) \qquad , \qquad \psi=e^{-\rho^2} (\frac{3}{2}-\rho^2) \qquad (m=0)$$となります。
ℓ=0よりm=0なので、縮退度は1です
(n,ℓ)=(0,2)のとき
エネルギーは$$E=\hbar \omega (2 \times 0 +2 +\frac{3}{2})=\frac{7}{2} \hbar \omega$$となります。(n,ℓ)=(1,0)の場合と確かに一致しています。
波動関数は
$$R=e^{-\rho^2 /2} \rho^2 \qquad , \qquad \psi=e^{-\rho^2} \rho^2 Y_{2m}(\theta,\phi) \qquad (m=0,\pm 1,\pm 2)$$となります。
ℓ=2より、mの絶対値は0,1,2となります。よって、mの個数は5個なので縮退度は5です。
縮退度のまとめ
(n,ℓ)=(1,0)の時の縮退度は1
(n,ℓ)=(0,2)の時の縮退度は5
でした。
したがって、第二励起状態の縮退度は1+5をすればよいので、縮退度6です。
まとめ
自分が演習をしていて時間がかかった問題だったので今回載せました(自分のためにも)。
理解度は浅く、自分の手で計算した式を載せているだけなので間違いがあるかもしれません。また、今後勉強していく中で追加していく項目もあると思います。
その点をご了承ください。
理系大学生や、文学を読むのが好きな方のために、こちらのページで無料で多数の本が読めるリンクをまとめています。非常に有益ですので是非お読みください。